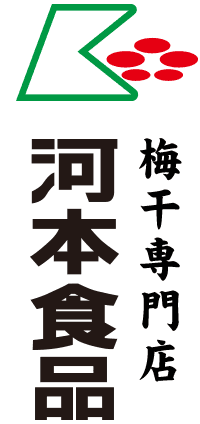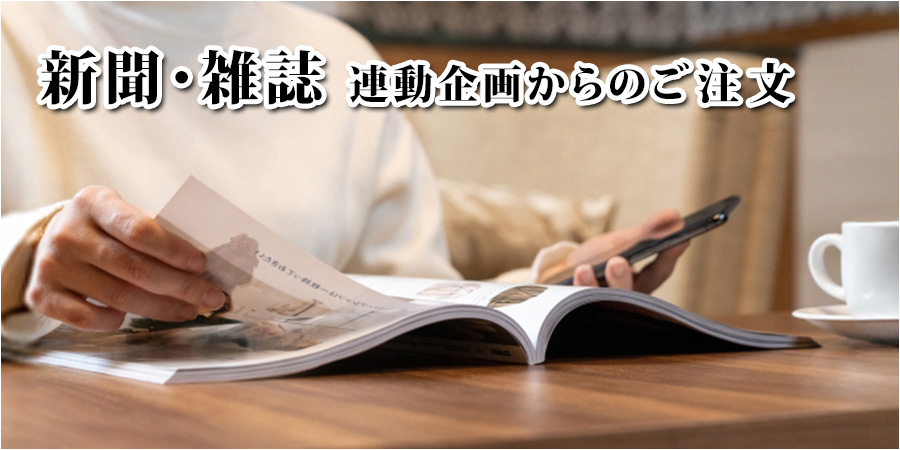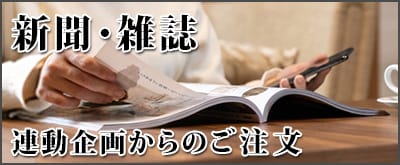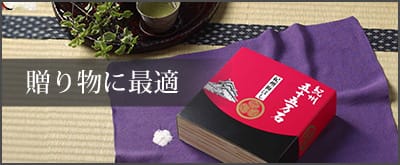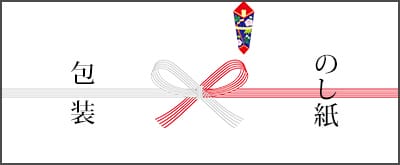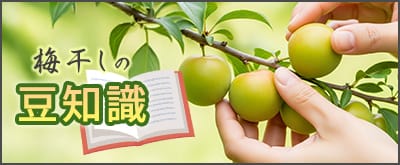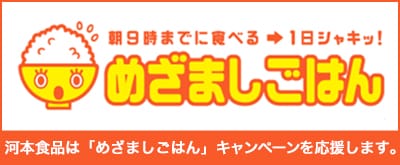梅干しの豆知識
紀州「南高梅」はいつ誕生したの?
まず、みなべ・田辺地方での梅栽培の始まりは、江戸時代にまでさかのぼります。
1620年頃、この地方では米が育ちにくく、重税や生活の困窮に悩まされていた農民が、竹や梅しか育たない「やせ地」は免租地となることから、重税を免れる意味もあって梅を栽培したことが、本格的な栽培の始まりです。
また、当時の田辺藩がやせ地や山の斜面での梅栽培を奨励し、保護政策を行ったことから、この地方を中心に梅の栽培が広がったとも伝えられています。
(ちなみに、このころの梅は「やぶ梅」と言われ、生命力は強いが、果肉が薄く小粒の梅でした)
梅の栽培が急激に増加したのは、明治40年以降で、これは日清(明治27~28年)・日露(明治37~28年)戦争による兵糧食としての梅干需要の増加によるものでした。
この時期、日高郡山田村(現:みなべ町)にて内中源蔵翁(1865~1946)が私財を投じて不毛の地を開墾し、梅を植えました。また、自ら加工場を建てることで、梅の生産から梅干加工、販売までを一手に行う事業を興し、成功をおさめました。
この経営方法が周辺に広まり、当地方の梅栽培が大きく飛躍する基礎となりました。
内中源蔵翁の偉業を称えるために、毎年2月11日「梅まつり・梅供養」が行われています。
そして、みなべ地方で梅の栽培が行われれるなか、「南高梅」が誕生したのは、昭和40年です。
昭和25年当時、市場の安定を目的に、この地に適した梅を選抜するため「優良母樹調査選定委員会」が設立されました。この委員会の委員長を務めたのが南部高等学校園芸科の竹中勝太郎教諭であり、同校園芸科の生徒たちも調査に関わりました。
5年もの調査の結果、数多くある品種の中から、最も優秀な成績を残した品種「高田梅(たかだうめ)」が選定されました。
この調査に深く関わった南部高等学校(通称「南高(なんこう)」)の教諭である竹中勝太郎氏と生徒たちの尽力に敬意を表して、「南部」の「南」と「高田梅」の「高」を組み合わせて「南高梅(なんこううめ)」と命名されました。
こうして南高梅は誕生し、昭和40年(1965年)に、農林省に品種登録されました。
現在、「南高梅」は、みなべ町で栽培される梅の8割を占め、梅のトップブランドとして日本国内はもとより、世界にもその名を馳せています。
梅干しが出来るまで

- 1.収穫
- 梅の花は厳しい寒さも忘れさすかのように二月頃に小さな白い花をつけて春の訪れを待ち、六月に新鮮な実がなり、完熟した実を収穫します。

- 2.洗浄・選別
- 一粒一粒、丹念に手もぎによって収穫された良質の梅だけを厳選し、洗浄選別します。

- 3.漬込み
- 選び抜かれた梅たちを天然塩だけで約一カ月半漬け込みます。

- 4.土用干し
- 一カ月半漬け込まれた梅は、梅雨明けと共に七月下旬から自然の恵みの中で三日三晩、天日干しし、梅ぼしとなります。

- 5.調味・漬込み
- 時代と共に移り行くニーズに応え、より低塩化に、また、かつお節こんぶ、しそ等により、食べやすく喜んでいただける味覚に調味し、漬け込みます。

- 6.包装・検品
- 厳重な衛生管理の元に仕上がった梅を検査し、良質な梅だけを容器に一粒一粒、思いを込めて詰めていきます。

- 7.お届け
- 心のこもった梅を全国のお客様に迅速に且つ安全にお届けします。